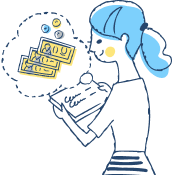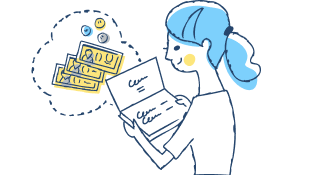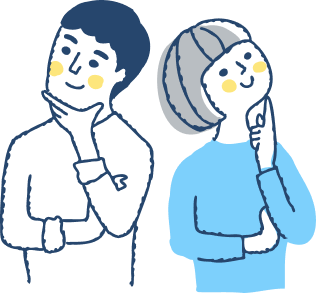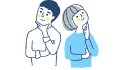死亡保険とは何か、必要性と正しい選び方を理解して、後悔のない備えをしましょう!
自分自身や家族のために、最初に検討する保険の一つが死亡保険ではないでしょうか。
皆さんが必要最低限の範囲で納得して死亡保険を選択できるよう、あなたにとって必要かどうか、保障の選び方のコツをご紹介していきます。
人が亡くなるとどんなお金が必要になるの?
死亡保険は主に、人が亡くなった時に必要となるお金をカバーするためのものです。
まずは人が亡くなった際に、どんなお金が、どのくらいかかるのかを理解しましょう。
主なものとしては以下が挙げられます。
1. 遺された家族の生活費
生命保険文化センターの調査(2021年)では、世帯主に万一のことがあった場合に、遺された家族のために必要と考える生活資金総額の平均は、5,691万円でした。
しかし遺された家族が「専業主婦(夫)の配偶者の場合」と「専業主婦(夫)の場合」、「共働きの場合」では、それぞれ必要になる生活費は大きく異なります。
専業主婦(夫)の配偶者(収入有)が遺された場合
子どもがいない場合は、配偶者自身に収入があるため特に生活費は不要です。
子どもがいる場合は、家事の外注にかかる費用やベビーシッターにかかる費用を見込む必要があるかもしれません。
専業主婦(夫)が遺された場合
子どもがいない場合であれば、配偶者が仕事に就くまでの一定期間分の生活費の準備が必要でしょう。
子どもがいる場合は、配偶者が仕事に就くのが難しい場合にも備えて、最低でも子どもが独立するまでは家族全員の生活費を準備しておくと良いでしょう。
共働きの場合
子どもがいない場合は、特に子どものための生活費は不要ですが、パートナーがしばらく仕事ができないことなどを考慮して、一定の生活費を準備しておくと良いかもしれません。
さらに、子どもがいる場合は、家事の外注やベビーシッターなどにかかるお金も準備しておくと安心。また、遺された妻(夫)の収入が少なく、亡くなった人の収入と大きな差がある場合は、その分上乗せする必要もあります。
2. 子どもの教育費
教育費は進学コースによって異なります。
進学コースごとの教育費の目安は下の表とおりですので、ご自身に当てはめて考えてみましょう。
3. 葬儀費用やお墓代などの死亡整理金
葬儀にかかる費用の他、お墓代、宗教者へのお礼(お布施など)に相当のお金がかかることもあります。
例えば、葬儀費用として必要と思われる金額として、平均約184万円かかると言われています。(※1)
お墓の管理費もかかりますし、戒名の位が高いとさらにお金がかかることもあります。
こうした費用について、日頃なかなか考える機会はないかもしれませんが、死亡保険の検討の際には、確認しておくとよいでしょう。
※1 鎌倉新書「第4回お葬式に関する全国調査」(2020年)
必要保障額の決め方は?
必要保障額を決める際には、残される遺族に必要となるお金と、入ってくるお金を理解しましょう。
入ってくるお金とは、各種遺族年金や企業からの弔慰金等を指します。
マネーフォワードの生命保険では、入ってくるお金部分の大半である公的保険制度の理解をすることが、無駄に保険に入らないためにも重要だと考えています。
必要保障額は、「遺された家族に必要となるお金」から「遺された家族に入ってくるお金」と自身や家族の「金融資産」を差し引いた「不足分」の金額となります。
マネーフォワードの生命保険では、簡単に無料で、あなたにとって必要な保障額をシミュレーションできるツールをご用意しておりますので、ぜひお試しください!
とはいえ、細かく必要保障額を見ていくのは大変ですし、必ずしも金融資産を削って生活をしたいわけではない方もいると思います。
そうした方は、マネーフォワードの生命保険の引受保険会社であるライフネット生命がご紹介している、以下のような考え方も参考にしてみましょう。
例えば年収500万円の人が亡くなり子どもがいない場合は、500万円×3年=1500万円。
子どもがいる場合はこれに教育費をプラスします。このように家族構成や年収によって、 必要保障額の目安を考えていくこともできます。
ぜひ、ご自身や家族が納得して安心の備えを出来る形で必要保障額を考えてみてはいかがでしょうか。
必要な保障額を踏まえて、まずはあなたの保険料を見積りをしてみましょう!
保険期間の決め方は?
保障金額だけでなく、適切な保険期間を設定することも大切です。
「何のために備えるのか」「どのくらいの保障が必要なのか」をはっきりさせましょう。
結婚や出産、住宅購入や子どもの独立などのライフイベントが起こるたび保障の必要性や必要な保険期間も変化しますので随時見直しを行うことをおすすめします。
まずは、生年月日と性別を入力するだけで簡単に保険料の見積りが出来る、10秒見積りでどのくらいの保障をいくらで備えられるのかを理解することから始めましょう!
出典:
他の記事も読んで、
かしこく保険を選びましょう!
マネーフォワードの
生命保険とは?
募集文書番号:LN_BB_PBD-297